限度額適用認定証とは、どのような制度ですか?
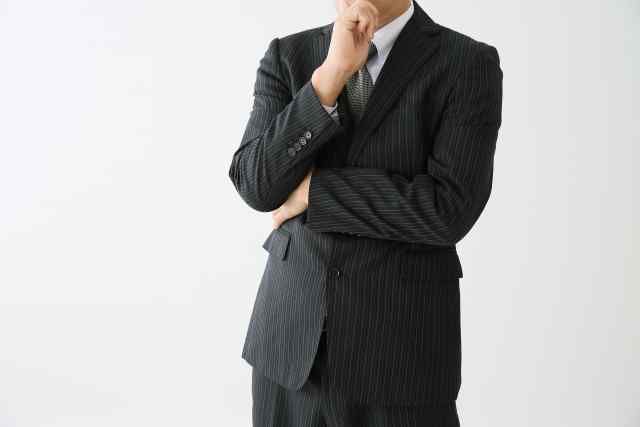
【質問】
従業員から、限度額適用認定証を発行して欲しい、と依頼されたのですが、どのようにすれば良いでしょうか?
また、限度額適用認定証とは、どのような制度で、高額療養費制度との関係は、どのようになっているのでしょうか?
【回答】
限度額適用認定証は、各都道府県の健康保険協会へ発行を依頼することとなります。
限度額適用認定証が発行されると、医療機関等に対して健康保険の自己負担額の限度額までの支払いで治療等を受けることができます。
【解説】
健康保険制度においては、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、後で払い戻される制度として高額療養費制度があります。
つまり、高額療養費制度は、一旦、>医療費を全額支払う必要があります。
もちろん、今でも従来通りに申請しても良いのですが、現在では、限度額認定適用証制度が創設されました。
限度額認定証は、各都道府県の健康保険協会で発行してもらいます。
限度額適用認定証を発行してもらうと、医療機関等に自己負担限度額のみ支払えばよくなります。
自己負担限度額を超えた分については、医療機関等が国に請求することとなります。
ところで、この限度額認定証を発行してもらう時に1つ注意する点があります。
限度額適用認定証の有効期限は、原則1年間なのですが、有効期限の初日は、原則、申請月の1日となります。
つまり、例えば、1月20日に入院して、2月に入ってから限度額適用認定証を申請した場合、限度額適用認定証の有効日は、原則2月1日からとなります。
となると、1月に支払った医療費が自己負担限度額を超えていたとしても、限度額適用認定証を使うことはできず、1月分については、従来通りの申請となります。
ただし、医療機関等が、この場合で言えば、1月分の医療費の精算をストップしておいてくれて、それを健康保険協会が確認できれば、前月1日を初日とする限度額適用認定証を発行してくれるようです。
ただ、これは、静岡県健康保険協会で聞いたことなので、各都道府県によって取扱が違うかもしれないので、その際には、ご確認下さい。
ところで、高額療養費制度は、被扶養者が支払った一定額以上の医療費も合算することができました。
そのため、限度額適用認定証は、被扶養者の分も発行することができます。
被保険者自身が、入院等する場合には、会社側もある程度把握することが出来るかと思いますが、家族の入院等までは、なかなかわかりずらいところもあるかと思いますので、経営者の方は、従業員の方に限度額適用認定証制度を適時周知すると良いかと思います。
最後に、限度額認定証の発行には、1週間から10日程かかります。
病院によっては、医療費の精算時に限度額認定証の提示が無ければ、通常通り医療費を支払わなければならなくなる場合もあります。
ですから、急な入院の場合は仕方が無いですが、予め入院の予定がわかっている場合には、早めに発行の手続きを取っておくと良いと思います。
なお、現在(令和7年1月)では、マイナンバーカードと保険証を紐づけした場合(マイナ保険証)には、限度額適用認定証が無くても、マイナ保険証がその代用とすることができるようになってきています。
ただ、全ての医療機関がそれに対応しているわけではないので、入院等する場合にはあらかじめ医療機関にご確認下さい。
【まとめ】

高額療養費制度は、同一月内に発生した医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、その超過分が後から払い戻される仕組みです。
ただし、一度全額を支払う必要があるため負担が大きい場合もあります。
この点を改善するため、限度額適用認定証制度が設けられました。
限度額認定証を取得すれば、医療機関等で限度額を超える自己負担額を支払わずに済む仕組みです。
限度額認定証は健康保険協会で発行され、有効期限は原則1年間で、申請した月の初日から適用されます。
また、高額療養費制度では、被扶養者の医療費も合算できるため、扶養家族の分の限度額適用認定証も発行可能です。
経営者や会社は、従業員にこの制度を周知することが重要となります。
発行には1週間から10日かかるため、入院予定がある場合は早めの手続きがおすすめです。
なお、マイナンバーカードと保険証を連携した「マイナ保険証」があれば、認定証がなくても代用可能な場合がありますが、すべての医療機関が対応しているわけではないため、事前確認が必要です。

