シリーズブラック企業にならないための労務管理⑪ 労務管理の土台 法定三帳簿
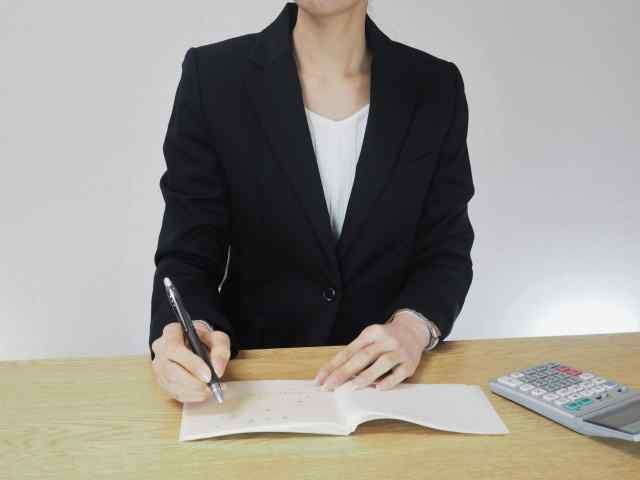
今回は、帳票の整備の重要性についてご説明したいと思います。
労務管理では、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を法定三帳簿と呼びます。
労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、これらの帳票の整備は、経営者の方が想像している以上に重要なことです。
なぜなら、例えば自社の労務管理の現状を把握しようとする場合や、あるいは自社が抱える問題点または改善点を明確にする場合、賃金台帳や出勤簿が必ず必要となります。
例えば、人件費の抑制を図ろうとした場合に、給料がどのように支払われているか分かる書類がなければ、改善に着手することは絶対にできません。
人件費の抑制や労働時間の削減といった問題は、労務管理の問題だけにとどまらず、経営全体の問題となります。
つまり、賃金台帳や出勤簿、このような帳票が整備されていなければ、経営改善を行うことすらできないのです。
私はこれまで数多くの企業と接してきました。
成長する企業は間違いなく、帳票の整備が行き届いています。
ですから、会社が発展・成長していくためには、帳票の整備というものは本当に不可欠なものとなります。
今回のブログでは、帳票に関する法律的な事項、そして帳票が果たす役割についていくつかの面から分かりやすく解説していきたいと思います、是非最後までお読みいただければと思います。
帳票の様式について

それでは本題に入っていきたいと思いますが、その前に一つ用語についてご了解いただきたいことがあります。
先程から「帳票」という言葉を使ってしまうが、この「帳票」という言葉はあまり馴染みがないかと思います。
ですから、今回のブログでは、単に「書類」あるいは「労務管理の書類」という言葉を使わせていただきたいと思います。
その点をご了解いただきたいと思います。
それでは本題に入っていきたいと思います。
まず、労務管理において重要な書類が三つあります。
それが冒頭にも書きましたが、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿です。
これらは、労務管理の法定三帳簿と一般的に言われています。
ここでまた「帳簿」という言葉が出てきましたが、これも「書類」と同じ意味で使われています。
この労務管理の法定三帳簿が、労務管理を行う上での土台、つまり最も重要な書類となります。
それでは、それぞれの書類についてご説明していきたいと思いますが、その前にこれら三つに共通することをお話ししたいと思います。
これらの書類について会社は整備しなければなりませんが、必要な事項が記載されていれば、様式は任意のもので構いません。
法律で特定の様式にしなければならないと決まっているわけではありませんので、様式自体は任意で大丈夫です。
ただし、あくまで必要な事項が書かれていることが前提となりますので、ここは注意して下さい。
労働者名簿について

それでは最初に労働者名簿についてお話ししたいと思います。
労働基準法では、労働者ごとに名簿の作成を義務付けていいます。
ただし、日雇い労働者に関しては作成の義務はありません。
労働者名簿には、以下の事項を記載する必要があります。
①氏名
②生年月日
③性別
④住所
⑤従事する業務の種類
⑥履歴
⑦雇入れ年月日
⑧退職年月日と事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)
このような事項が記載されていれば、様式はどのようなものを使っていただいても問題ありません。
フォーマットについては厚生労働省がインターネットで公開していますので、それも参考にしていただければと思います。
労働者名簿は、労働者ごとに作成することがポイントとなります。
賃金台帳について

次に賃金台帳ですが、賃金台帳は、会社の労働者に対する賃金の支払い状況や勤務時間などを記載した書類となります。
賃金台帳も、労働基準法で作成が義務付けられています。
労働基準法では、賃金台帳には、以下の事項が必要記載事項として定められています。
①氏名
②性別
③賃金計算期間
④労働日数
⑤労働時間数
⑥時間外労働の労働時間数
⑦休日労働の労働時間数
⑧深夜労働の労働時間数
⑨基本給や手当等の種類とその金額
⑩控除項目とその金額
現在では、多くの会社が、賃金計算給与ソフトを使って計算していると思います。
通常、給与ソフトであれば賃金台帳を作成する機能がありますので、それを用いていただければと思います。
ただ、エクセル等で作成する場合は、先ほど述べた必要事項を必ず記載する必要があります。
法定三帳簿の中でも、特に賃金台帳は重要ですので、しっかりと整備する必要があります。
出勤簿について

最後に出勤簿についてご説明したいと思います。
先ほど述べた労働者名簿や賃金台帳については労働基準法で作成が義務付けられていると言いましたが、出勤簿については、実は労働基準法では特段の定めがありません。
ただし、厚生労働省が出している「労働時間の適正な把握のための使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」中で、労働基準法の第109条に基づいて労務管理に関係する重要な書類を保存しなければならないとされています。
そして、その重要な書類として出勤簿が該当するとされているため、出勤簿も必ず作成しなければならない書類となります。
元々、労働時間の管理は会社使用者の義務ですので、管理するには何らかの書類が必要です。
そういった意味でも、出勤簿の作成義務があります。
ところで、出勤簿については、必ずタイムカードを使わなければならないのか?という質問をよく受けます。
タイムカードが、一番望ましいのですが、出勤簿の趣旨は適正な労働時間を管理することですので、適正に労働時間が管理できれば必ずしもタイムカードでなくても大丈夫です。
パソコンやICカードを使って、適正に労働時間を管理できればそれで十分です。
繰り返しになりますが、労務管理において重要な書類として労働者名簿、賃金台帳、出勤簿をしっかりと整備しなければなりません。
まずここを理解していただきたいと思います。
ただし、書類の内容等を理解するだけでは意味が全くありません。
実際に必要な書類をしっかりと整備していただく必要があります。
その点は、是非正しくご理解していただければと思います。
保存期間について

ここでは労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の保存期間についてご説明したいと思います。
労働基準法では、2020年に法律改正があり、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿に関して原則5年間の保存期間を定めています。
ただし、当分の間は、経過措置として3年間とされています。
ですから、現時点(2024年)では、労働者名簿等は3年間保存すれば良いのですが、いつ経過措置が廃止となるかわからないし、経過措置の廃止を知らないでいる可能性もありますので、今の時点で5年間保存する方が無難と言えるかもしれません。
ところで、保存期間で問題となるのが、起算日です。
つまり、いつの時点から5年間書類を保存しなければいけないのか、ということです。
まず、労働者名簿の起算日ですが、労働者の死亡または退職の日からとなります。
ですから、労働者が、退職した後も退職日から3年間は、労働者名簿を保存しなければいけない、このような形となってきます。
次に賃金台帳ですが、賃金台帳の保存期間の起算日は、「最後に賃金台帳を記録した日」と「賃金台帳に記録した賃金の支払日」を比べて、よりあとの日付を起算日としています。
例えば、月末締めの翌月15日支払いの会社の場合で、例えば6月分の給与額を7月15日までに賃金台帳に記録すれば、支払日の方があとの日付となりますので、7月15日が保存期間の起算日となります。
しかし、6月分給与を支払ったあとに、その額を賃金台帳に記録すれば、記録日が起算日となります。
最後に出勤簿の保存期間の起算日ですが、出勤簿につきましては、完結の日とされています。
完結した日というのは、労働者が最後に出勤した日です。
ただし、最後に記載された出勤日より賃金支払期日が遅い場合、賃金支払期日が起算日とされています。
従って、賃金締切日が月末で、給与支払い日が翌月15日の場合で、6月末日が最終出勤日には、最終出勤日を含む6月分の給与の支払いが7月15日となりますので、7月15日が保存期間の起算日となります。
ところで、通常給与は、最終出勤日以降に支給されますので、出勤簿の保存期間の起算日は、最終給与支払い日と規定すれば良いと思われるかもしれませんが、稀なケースですが、最終出勤日以前に給与が支給されるケースが考えられます。
例えば、先程と同じ賃金締切日が月末で、給与支払い日が翌月15日の場合で、退職日が7月15日の場合で、6月末締め分の給与と7月分の給与を7月の出勤予定日を基に合わせて支給してしまうケースが考えられます。
この場合、給与支払い日より最終出勤日の方が後となりますので、7月15日が保存期間の起算日となります。
なお保存方法についてですが、法律が規定された時点では紙ベースで保存することを想定していましたが、現在ではIT化が進んでいますので、必要なときに、紙ベースで出すことができれば、電子データでの保存することも認められています。
パートタイマー、アルバイトも賃金台帳等の作成が必要

これからお話することは、非常に重要なこととなりますが、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の作成は、パートタイマーやアルバイト等の労働者についても作成する義務があります。
つまり、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の作成正社員だけが対象というわけではありません。
名称に関わらず正社員以外の労働者に対しても、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を作成する必要がありますのでご注意して下さい。
なお、日雇い労働者についてですが、労働者名簿だけは、作成義務がありません。
つまり、日雇い労働者であっても、賃金台帳や出勤簿を作成する必要があるのでご注意して下さい。
労務管理書類の役割とは?

ここでは労務管理の書類が持つ役割について、いくつかの点からお話ししたいと思います。
まず、労務管理の書類に限らず、会社が成長し、経営を安定させるためには様々な書類の整備が重要というのは、誰もが理解していることだと思います。
先程も少しお話ししましたが、経営が安定している会社で、書類の整備がずさんな会社というのはまずありません。
逆に言えば、書類の整備がずさんな会社というのは、いわゆるどんぶり勘定の経営となってしまいます。
そして、それはブラック企業の状態へと繋がってきます。
書類が整備されていなければ、当然法律違反が起こりやすい状態となってきます。
まずそのような意味で、書類の整備が重要性であるということは、理解いただけると思います。
そして、それ以外にも、もう少し細かい点からお話ししたいと思います。
なぜ書類の整備が必要かと言いますと、労働者を雇用している場合には、労働基準監督署の調査を受ける可能性があるからです。
労働基準監督署の調査を受ける場合には、賃金台帳、出勤簿等の提出が必ず求められます。
もし賃金台帳、出勤簿等を提出できなければ、当然指導または是正勧告の対象となります。
労働基準監督署から指導また是正勧告を受けると、それが改善されるまで、労働基準監督署の指導が続きます。
ですから、書類が整備されていない状態で、労働基準監督署の調査を受けると、経営者にとって精神的負担が大きくなります。
また最終的に何処かの段階で書類を整備しなければいけないため、そのための時間と労力がかかってしまいます。
ですから、労働基準監督署の調査が行われても問題がないようにするために、賃金台帳、出勤簿等の整備は必要となります。
そしてもう一つ、労務管理において書類の整備が重要となる点があります。
それは助成金です。
助成金は、適正な労務管理を行っていることが条件となっていますので、助成金を申請する場合には、このような書類を提出するケースが非常に多いです。
そして、その内容がしっかりと整備、法律の基準を満たしている必要があります。
もし必要な書類が整備されていなければ、せっかく助成金を受給できる機会にもかかわらず、助成金を申請することができなくなってしまいます。
助成金活用の面からも、労務管理書類の整備は、重要なポイントとなります。
ここで少し余談になるのですが、数年前の新型コロナウイルスの感染が拡大し始めたときに、飲食店を始め、多くの会社が休業を余儀なくされました。
会社を休業するということ、当然、労働者を休業させるわけです。
ところで、労働基準法には、労働者を休業させた場合には、休業手当を払わなければいけないという法律があります。
会社側からすると、売り上げがないのに労働者に休業手当を払うということになると、会社が立ち行かなくなってしまう可能性があります。
となると、労働者の雇用が守られなくなってしまう、このようなケースが想定されます。
ですから、国としては労働者の雇用を守るために、会社が払った休業手当の何割かを支給するという助成金の制度を設けています。
これが雇用調整助成金です。
当時、この雇用調整助成金が、注目を浴びました。
ただ、この雇用調整助成金は、申請書類を揃えるのが非常に大変でした。
当時マスコミも申請書類の多さに複雑さに、批判的な報道が多かったのです。
私も雇用調整助成金を何十回も申請しましたが、最初の頃は本当に大変でした。
途中から書類は簡素化されたのですが、それでも大変なところはありました。
ただし、決して国の肩を持つわけではないのですが、大変とはいえ、提出する書類は、本来会社が整備しておかなければいけないものばかりでした。
今回ご説明した賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、このような書類です。
ですから、日頃からしっかりと整備しておけば、確かに揃える労力は大変だったかもしれませんが、決して揃えられない書類ではありませんでした。
しかし、飲食店等、書類の整備がされていない業種が多かったため、雇用調整助成金の申請を諦めた会社が多数あったと聞いています。
ですから、このような意味からも、書類の整備は、労務管理において重要なポイントと言えます。
会社経営においても労務管理の書類の整備は重要

ここでは、会社経営においての労務管理の書類の重要性についてお話したいと思います。
「確かに労務管理の書類の重要性はわかるけど、なかなかそこまで手が回らないし、書類を一生懸命整備しても、それ自体売り上げに繋がらない。」とおっしゃる経営者もいらっしゃるかもしれません。
確かに労務管理の書類を一生懸命整備したとしても、その行為自体は売り上げには繋がりません。
しかし、別の視点から考えてみていただきたいのです。
先程も言いましたように、もし書類が整備されていない状態で、労働基準監督署の調査を受けたら、必ず書類を整備しなければなりません。
おわかりかと思いますが、同じ書類を作るにしても、その都度作る場合と、後でまとめて作る場合とでは、後でまとめて作る方が圧倒的に大変です。
時間もかかりますし、ミスも起こりやすくなります。
ですから、それだけ時間と労力が無駄になってしまいます。
誰がやるにしても、大切な時間が奪われてしまいます。
時間が奪われるということは、経営的な観点から見れば、大きな損害となります。
また助成金もそうです。
助成金というのは、国から出るお金で返す必要がありません。
しかも経費がかからないため、純利益に近いものです。
ですから経営者にとって非常に魅力的な制度です。
しかし、書類が整備されていなければ、せっかく助成金を受給できる機会を逃してしまうとことも考えられます。
これは、会社にとって大きな損害です。
つまり、書類の整備というのは、その行為そのものは直接売り上げの増大には繋がらないかもしれませんが、間接的に見れば、貢献度は非常に大きいものと言えます。
ですから、必要な書類の整備をするということは、会社の経営においても重要なことです。
このような視点からも、労務管理の書類の重要性をご理解いただければと思います。
労務管理の書類整備のテクニック

「確かに先生がおっしゃるように労務管理の書類の整備が重要なのはわかります。ただ、日々なかなか忙しくてそこまで手が回らないのです。」とおっしゃる経営者もいらっしゃいます。
確かにそれは、私もよくわかります。
なかなか書類まで手が回らないのが実情かもしれません。
そこで、それに関して一つ提案というか、私の経験をお話したいと思います。
実は私、社会保険労務士として独立する前にサラリーマンの時代があったのですが、そのサラリーマンの時に損害保険の代理店業務務に従事していたことがあります。
当初は、別の部署にいたのですが、異動で保険代理店業務に従事することになりました。
当時の損害保険の業務というのは、今のようなキャッシュレス化、ペーパーレス化が進んでいなくて、保険料を現金でもらったり、申込書に署名捺印をもらったりしていました。
そのために書類整備や経理帳簿の作成が非常に大変でした。
損害保険代理店というのは金融機関ですから、経理帳簿や領収書等の書類に関する目が非常に厳しく、書類整備が非常に大変でした。
しかし、膨大な数の契約更新業務や新規案件の開拓等、普段は営業業務に忙殺されしまうため、異動した当初は書類の整備になかなか時間を費やすことができませんでした。
ですから、現在どのような契約があるのか、全手数料のうち自動車保険の手数料の割合はいくらなのか、といったことが全然わかりませんでした。
本当に最低限の書類の整備しかやっていませんでした。
ですから、私はこのままだとまさにどんぶり勘定の経営になってしまうと思い、何とかしなければいけないと思いました。
ところで、私自身は保険代理店業務に従事していましたが、私が勤務していた会社は、スーパーマーケット業が主な業種でした。
ですから、土曜日や日曜日に出勤することが多かったのです。
それに対して、土日が休日の契約者も多く、また保険会社が、土日が休みですから、保険会社からの問い合わせや担当者との打ち合わせもなく、土日は比較的時間に余裕がありました。
ですから、私は少し考えまして、日々は、最低限の書類管理だけして、土曜日の午前中3時間を書類整備の時間に充てることにしました。
3時間書類の整備に充てるとなると、当然その時間は営業ができなくなるわけですから、最初は少し怖いところもありました。
しかし、この3時間だけは絶対に書類の整備をするということで、整備の時間に当て始めました。
そうすると1ヶ月、2ヶ月経つと、書類が整備されていて、自分の中で業務の全体像がすごくすっきりと見えるようになったのです。
そして、何が一番良かったかというと精神的な安定です。
これは皆さんも経験があると思いますが、いついつまでに書類を作らなければいけないのに、手を付けないでいるのは、ストレスになってしまい精神的に良くないです。
ですから、毎週土曜日午前中3時間書類の業務を行うようになってから、書類に対して、ストレスを感じなくなり、精神的にすごく楽になりました。
そして業務も効率化されました。
先程言いましたように業務全体像が見えてきたこともありますが、それ以外にも、お客様から何か問い合わせがあった場合でも、書類が整備されているため、書類を探すこともなくなり、答えに要する時間が圧倒的に短くなりました。
ですから、1週間に1回でもいいですし、2週間に1回でも結構です。
必ずその時間は書類の整備に充てる、その時間は死守する。
これは本当に効果が高いです。
そして、私は今もやっています。
例えば、確定申告です。
確定申告をご自分でやられた方はわかると思いますが、1年間領収書とか経理書類を放っておくと、確定申告が近づくと胃が痛くなるかと思います。
私も最初はそういうときもありましたが、途中から毎月定期的に書類を作るようになってからは、確定申告の時期が来てもそんなに苦にならなくなりました。
ですから、一定時間を書類の整備に充てるというのは本当に効果が高いですし、経営的にも非常に貢献するところが多いですので、ぜひ試していただければと思います。
余談になってしまいましたが、参考になさっていただければと思います。
まとめ

今回は、適正な労務管理の土台ということで、労務管理に関する書類の整備の重要性についてお話してきました。
繰り返しになりますが、労務管理に関する書類を整備するということは、経営者が考えている以上に重要なことです。
なぜなら、労務管理の問題である労働時間の削減や人件費の抑制は、労務管理の問題にとどまらず、経営全体の問題となるからです。
したがって、経営を改善するためには、労務管理に関する書類の整備が本当に必要不可欠です。
是非今後の労務管理の向上に今回のブログをお役立ていただければと思います。

