社員を解雇すると助成金を受けられなくなると聞いたのですが・・・。
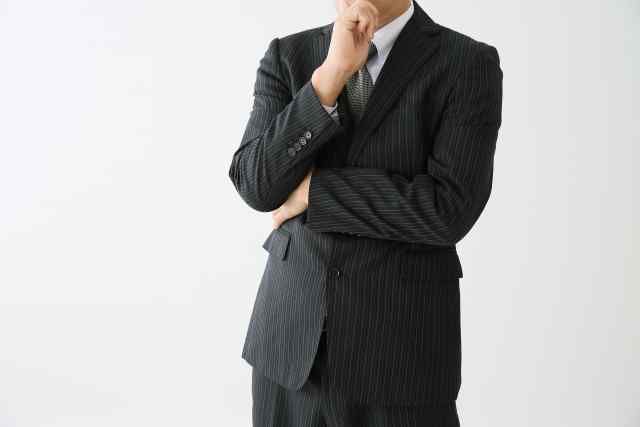
現在、当社では、問題がある社員の解雇を検討中ですが、社員を解雇すると助成金を受給することができなくなると聞きました。
当社では、現在、いくつかの助成金の利用を考えているのですが、社員を解雇した場合には、本当に助成金を受けることができなくなってしまうのでしょうか?
【回答】
多くの助成金には、社員を解雇等した場合に一定期間、助成金の受給を制限する要件が定められています。
【解説】
助成金は、返済不要でしかも使用目的も問われないため、経営者にとっては非常に魅力的な制度と言えます。
ところで、助成金制度は、雇用保険制度の一環として行われていて、雇用機会の維持及び増大を図った企業に支給されます。
そのため、社員の解雇等は、助成金制度の趣旨と真逆な位置にあると言えます。
従って、ご質問にあるように、多くの助成金制度では、社員を解雇等した企業に助成金受給を一定期間制限する要件が規定されています。
受給制限される期間は、あくまで一定期間であって、社員を解雇等したからといって、未来永劫に助成金を利用できなくなるわけではありません。
ただし、ここで注意すべき点は、受給制限される期間が助成金によって異なってきます。
例えば、母子家庭の母等の就職困難者をハローワークを通じて雇用した場合に支給される特定求職者雇用開発助成金の場合は、社員等を解雇した場合にその前後6ヶ月間は、助成金対象の社員を雇用しても助成金は支給されません。
それに対して人材開発支援助成金、制度導入コースでは、計画書を提出した日より6ヶ月前の日から支給申請書の提出日までに解雇があった場合には、助成金は支給されません。
つまり、計画書を提出した後に社員を解雇してしまうと、その計画書の期間内の申請が出来なくなってしまうこととなります。
このように、助成金の種類によって、解雇により支給制限の期間が異なってきますので、注意が必要となります。
なお、解雇制限につきましては、助成金の対象労働者を解雇等する場合には、更に厳しい制限が科せられる場合がありますので、詳細につきましては行政官庁等に確認して下さい。
次に離職理由についてもう少し詳しくお話したいと思います。
ご存知のように、労働基準法により、社員を解雇する場合には、原則、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うか、30日以上の解雇予告期間を設ける必要があります。
ところで、実務上では、いきなり社員を解雇するのではなく、退職勧奨を行う場合があります。
もし、社員が、退職勧奨に応じた場合には、労働契約の合意解約であり解雇ではないため、解雇予告手当の支払いは不要となります。(退職勧奨に応じてもらうために、何らかの金銭の支払いを提示する場合はあります。)
つまり、労働基準法では、社員が離職する場合、解雇と退職勧奨による退職では、その取扱いが異なってきます。
ところで、雇用保険の資格を喪失する場合、喪失理由は、次の3つに分類されます。
1.離職以外の理由
2.3以外の離職
3.事業主の都合による離職
これまで、社員を解雇等した場合には、一定期間助成金が不支給となる、とご説明してきましたが、具体的には、離職理由が、上記の3の「事業主の都合による離職」となった場合に、助成金は、解雇の制限を受けます。
ここで気を付けなければならないのは、「事業主の都合による離職」には、解雇だけでなく退職勧奨の場合も含まれるのです。(ですから、これまでの説明で解雇等と「等」を付けていました。)
実際、「事業主の都合による離職」には、解雇や退職勧奨以外にも、労働条件が明示された条件と著しく異なっていたなど、かなりの数が定められています。
詳しくはこちらをご参照下さい。
つまり、助成金が、一定期間支給制限を受けるのは、解雇だけでなく退職勧奨はもちろん、それ以外の場合でも助成金の支給制限を受ける場合があるのです。
今後、助成金を活用していく場合には、雇用保険の離職理由については、正しく理解することが重要だと言えます。
ちなみに、1の「離職以外の理由」とは、1つの企業で雇用保険の事業所が複数ある場合に、転勤等で所属する事業所が変わる場合で、2の「3以外の離職」は、自己都合退職の場合に使用されます。
【まとめ】

助成金は返済不要で使途の制限もなく、企業にとって魅力的な制度ですが、雇用機会の維持・増大を目的としているため、解雇を行った企業には一定期間、受給が制限される場合があります。
ただし、解雇後も未来永劫に助成金を利用できなくなるわけではなく、制限期間は助成金の種類によって異なります。
また、解雇だけでなく退職勧奨も「事業主の都合による離職」として扱われるため、助成金の支給制限を受ける可能性があります。
助成金の活用を検討する際は、雇用保険の離職理由について正しく理解することが重要です。

