解雇の種類と解雇手続き等について教えて下さい

「解雇」とは、会社が一方的に労働者との雇用契約を解除することを言います。
労働者にとっては、突然、生活の糧を絶たれてしまうわけですから、大きな問題となります。
そのため、解雇は大きなトラブルになりやすく、また、解決まで多大な労力と時間、そして時には高額な和解金等の支払いが必要となってしまう場合があります。
従って、経営者の方が解雇について正しい知識を有することは、事業経営を行っていく上で非常に重要なことと言えます。
本ブログでは、解雇の種類とその概要及び解雇する場合の手順等、解雇に関する基本的な事項を解りやすく解説してあります。
何故、解雇は大きなトラブルとなってしまうのか?

これからお話ししますが、解雇にはいくつかの種類がありますが、どの解雇であっても、労働者の意図に反して雇用契約が解除されることとなります。
労働者にとっては、突然、生活の糧を奪われてしまうこととなるわけですから、死活問題となり、簡単に「はい、わかりました。」とは、ならないのが常です。
また、大きな問題であるため、そこに感情論が絡んできて、「絶対にあの社長は許せない!」と結果的に裁判等に発展してしまうケースが多いので、他の労働トラブルとは違い、大きなトラブルになってしまう可能性が非常に高いのです。
ですから、誤った認識で労働者を解雇することは、非常に危険なことなのです。
ところで、こちらをご覧いただければわかりますが、解雇は、労働トラブルの原因の中でも常に上位にきています。
>>労働相談の内容(東京都産業労働局)
つまり、解雇トラブルはどの会社において、いつ起きても不思議は無いのです。
解雇の正当性、妥当性について

まず、解雇についてまず1つ押さえておいていただきたいポイントがあります。
先程、解雇は大きな労働トラブルに発展する可能性が高いと書きましたが、実は労働者を解雇すること自体は、多少正確性には欠けますが、違法行為ではありません。
元々、労働者を雇用するということは、労働者と雇用契約を結ぶことです。
となれば、解除できない契約というのは、基本的には有り得ないはずです。
もちろん、法律や契約内容によって規定されている、解除のための手続き等を守る必要はありますが、契約を解除する権利自体は、会社にも認められてしかるべきです。
では、何が問題となるのか?
まず、ここを押さえていただきたいのです。
労働者を解雇した場合、それを不服として労働者が訴えを起こす場合があります。
その場合、解雇した理由が、解雇するのに妥当性や正当性があるのか裁判等で判断されることとなります。
もし、裁判等で解雇した理由と解雇の処分とを比較した場合、解雇した理由が解雇するほどまでの妥当性や正当性が無いと判断されれば、不当解雇となってしまいます。
解雇トラブルの難しさは、どのような理由であれば、不当解雇にならないのか明確な基準が法律で定まっているわけではないのです。
ただ、ご存知のように、我が国では労働者保護の風潮が非常に強い所があります。
そのため、解雇が認められるためのハードルは、非常に高いと言えます。
つまり、解雇で押さえておいていただきたいポイントは、解雇すること自体が違法行為ではなく、解雇した労働者が訴えを起こした時に、大きなトラブルとなってしまう可能性が非常に高い、ここをまず押さえていただきたいと思います。
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら
解雇の種類

一般的に解雇の種類には次の3つがあります。
① 懲戒解雇
② 普通解雇
③ 整理解雇
また、これ以外に諭旨解雇と呼ばれる解雇もあり、また、解雇ではありませんが、退職勧奨という形もあります。
それぞれ、解雇に至るまでの過程が違いますので、1つずつ解説していきたいと思います。
その前に1つご理解していただきたいのですが、実は、それぞれの解雇には、法律上の定義があるわけではありません。
つまり、「懲戒解雇は、~である。」というように法律上定義されているわけではないのです。
ですから、それぞれの名称も法律用語ではなく、あくまで習慣的な名称なのです。
実は、この点が、解雇を正しく理解するする上で大きなポイントと言えます。
この点も、是非押さえていただければと思います。
では、それぞれの解雇についてご説明していきたいと思います。
懲戒解雇とは?

懲戒解雇は、社内の秩序を著しく乱した場合に、懲罰として労働者との雇用契約を解除するものです。
懲戒処分としては最も重い処分となります。
懲戒解雇に該当するケースは以下のようなものが考えられます。
・不正経理処理により多額の金銭を横領していた場合
・殺人・強盗・強姦等の重大犯罪により会社の名誉、信用を著しく損なった場合
・長期間に及ぶ無断欠勤
・重大な経歴詐称
・訓告、減給、出勤停止等の懲戒処分を繰り返し受けたにも関わらず改善されない場合
ただし、先程もお話ししましたが、解雇理由の妥当性、正当性が認められる基準が法律で規定されているわけではないので、解雇の妥当性、正当性は裁判等で個々のケースごとに判断されます。
ですから、例えば、同じ金額を横領した場合であっても、A社の場合には、解雇理由の妥当性や正当性が認められても、B社の場合には否定されるケースもあり得ます。
普通解雇とは?

先程も書きましたが、労働者を雇用するということは、労働者と雇用契約を結ぶことです。
そして、雇用契約によって労働者は会社に適正な労働力を提供する義務を負い、その労働力に対する対価を受取る権利を有します。
しかし、労働者が何らかの理由で適正な労働力を提供できない場合には、契約に不履行が生じるため、その理由をもって会社は雇用契約を解除、つまり解雇することができると考えられます。
このような解雇を普通解雇と呼ばれています。
懲戒解雇が、重大な問題を起こした場合に懲戒処分として解雇するのに対して、普通解雇かは、契約を履行できなくなったために解雇する、といったイメージとなります。
普通解雇が行われる理由としては、以下のようなものが考えられます。
・勤務成績または業務能率が著しく不良で、就業に適さないと認められたとき
・精神または身体の障害により職務に耐えられないと認められるとき
・事業の縮小、その他事業の運営上やむを得ず、社員の減少等が必要となったとき
ただし、ここでも注意しなければならないのは、懲戒解雇同様、解雇理由の妥当性、正当性が認められる基準が、法律で定められていないため、例えば、精神または身体の障害により職務に耐えられないという理由で解雇しても、裁判等で、「解雇に該当するほど、職務に耐えられないわけではない。」と不当解雇と判断されてしまう場合もあります。
ところで、先程挙げた解雇理由の最初の2つについては労働者側に原因がありますが、3つ目の「事業の縮小、その他事業の運営上やむを得ず、社員の減少等が必要となったとき」については、確かに、労働者が適正な労務を提供できなくなりますが、労働者側には基本的には非はありません。
そのため、他の普通解雇とは、通常分けて考えられます。
一般的に、事業の縮小、その他事業の運営上やむを得ず、社員の減少等が必要となったとき行われる解雇を「整理解雇」と呼ばれています。
では、次に整理解雇についてご説明していきたいと思います。
整理解雇とは?

整理解雇は、経営不振により、現状のままでは事業を継続していくのが困難な場合に、経営上必要な人員削減を行うための解雇であり、普通解雇の1つとされています。
ところで、整理解雇も、これまでお話ししてきた懲戒解雇や普通解雇と同様、売上が何パーセント以上下がったら、解雇の妥当性、正当性が認められる基準は、法律では規定されていません。
ただ、整理解雇については他の解雇とは違い、これまでの判例の積み重ねで、整理解雇が妥当、正当なものとなるための要件が、ある程度確立されています。
一般的に整理解雇の4要件と言われ、具体的には以下の4つとなります。
①人員削減の必要性
②解雇回避努力の度合い
③解雇される労働者の選択方法の合理性
④手続きの妥当性
整理解雇の4要件について
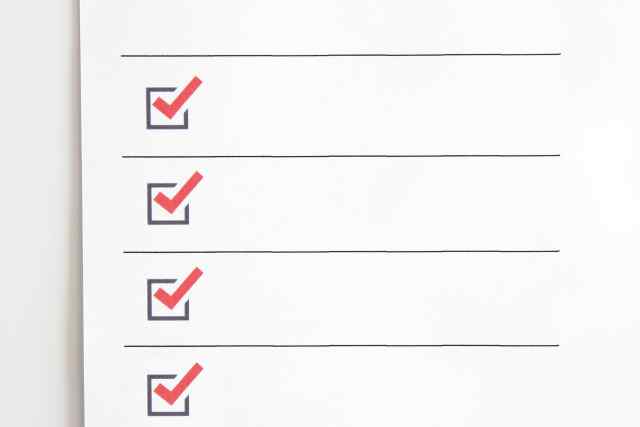
4要件は整理解雇を行う上で非常に重要となってきます。
ただし、それぞれの解説をお読みなっていただければわかるかと思いますが、各要件について具体的な基準が定められているわけではありません。
ですから、各要件がどこまで以上になれば、解雇の妥当性、正当性が認められるかは、結局は裁判等の判断によることとなってしまいます。
しかし、解雇整理の場合、この4つの要件がポイントとなることが確立されているので、他の解雇とは違って、ある程度の目安にはなるかと思います。
① 人員削減の必要性
これは、会社が事業経営を続けていくためには、どうしても人員の削減が必要であったのか?ということです。
この場合、何故、人員を削減しなければならないのか、売上等のデータや必要な削減人数等、具体的に説明できる必要があります。
② 解雇回避努力の度合い
これは、経営者は、解雇を避けるために、どの程度努力したかです。
具体的には、経費の削減、役員報酬の減額、新規採用の縮小又は停止、一時休業等が考えられます。
つまり、解雇は最終手段であって、それ以前に会社は可能な限りの努力をしなければならない、という考えです。
例えば、役員の報酬削減等、経営者側が痛みを被っていないのに、労働者にばかり痛みを強要するのでは、裁判等では、当然に理解を得られないこととなります。
③ 解雇される労働者の選択方法の合理性
これは、解雇される労働者の選択が、経営者の主観によって決められるのではなく、客観的、合理的かつ公平に行われる必要があります。
労働者を選ぶ基準は、年齢、勤続年数、扶養家族の有無、勤務態度、能力、労働者の身分(正規労働者か非正規労働者)等多々あると思いますが、どんな基準で選ぶにしろ、経営者の主観や恣意的に選ぶことは、客観性、合理性、公平性が欠けることとなります。
④ 手続きの妥当性
手続きの妥当性とは、会社が整理解雇の必要性を労働者や労働組合に十分に説明し、納得を得るために誠実な態度で協議する必要があります。
実は、整理解雇において、この手続きの妥当性は重要なポイントとされ、不誠実な対応や横柄な態度を取ると、他の要件に十分な妥当性、正当性があったとしても、解雇が無効とされる場合があるので注意が必要です。
一般的に解雇の種類は、上記に3つとされていて、解雇に至る理由を整理すると
① 重大な問題を起こしたことによる懲戒処分としての解雇(懲戒解雇)
② 能力不足や健康上の問題で雇用契約の履行が困難ために行われる解雇(普通解雇)
③ 経営悪化に伴い行われる解雇(整理解雇)
と大まかに分けることができるかと思います。
ところで、解雇には諭旨解雇と呼ばれるものがあります。
また、解雇ではありませんが、退職勧奨と呼ばれるものもあります。
「諭旨解雇」や「退職勧奨」は、これまでお話しした、懲戒解雇と普通解雇と密接な関係があるので、「懲戒解雇」や「普通解雇」を正しく理解する上でも重要となってきます。
難解な労務管理知識をわかりやすく解説!毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく完全無料メールセミナー「労務365日」のご登録はこちら
諭旨解雇とは?

諭旨解雇とは、懲戒解雇に相当する問題行動を起こした労働者に対して、会社が温情的な措置を講じて行う解雇を言います。
イメージ的には、懲戒解雇よりワンランク軽い処分と言えます。
では、温情的な措置とはどのようなものでしょう?
基本的には、退職金の支払いの有無を言います。
多くの退職金規程には、懲戒解雇の場合、退職金を支給しない又は減額する規定が盛り込まれています。
諭旨解雇とは、本来、懲戒解雇に該当するため退職金の全額又は一部を支払わないところを、会社が温情をかけることにより退職金の一部又は全額を支給して解雇するというものです。
ですから、諭旨解雇は、元々、諭旨解雇という種類の解雇があったわけではなく、懲戒解雇に相当する労働者に対して、せめて退職金だけは支払ってあげよう、という温情的な措置を講じって解雇するケースを諭旨解雇と称するようになったわけです。
ところで、諭旨解雇、懲戒解雇と退職金との関係で、経営者の多くが誤解している点があります。
ここまでお読みなると、「諭旨解雇の場合は、退職金は支給され、懲戒解雇の場合は、退職金は支給されない。」と思われた方も多いのではないかと思います。
実は、解雇と退職金との関係については、全く法律の規定がありません。
ですから、「諭旨解雇の場合には、退職金が支給され、懲戒解雇の場合には退職金が支給されない。」といった法律の規定があるわけではないのです。
元々、退職金自体も法律の規定が全くなく、会社に課せられた義務でもありません。
そのため、退職金規程の内容も、会社が自由に決めることができるものです。
つまり、「懲戒解雇の場合には、退職金を支給しない。又は減額して支給する。」といった規定は、本来は、単なる社内ルールに過ぎないのです。
実際、懲戒解雇より退職金を不支給した場合でも、労働者が訴えを起こし、裁判等で退職金の不支給は不当という判断が下されるケースもあります。
インターネット等で「懲戒解雇の場合には退職金は支給されず、諭旨解雇の場合には支給される。」といういかにも法律で決まっているかのような書き方がされている場合がありますが、それは全くの誤りです。
なお、解雇と退職金についてのご説明は、本題の趣旨と少し離れてしまいますので、これ以上のご説明は割愛させていただきますが、こちらのブログに詳しく書いてありますので、ご興味ある方は、是非、お読み下さい。
ここでもう1つ諭旨解雇についての注意点をお話ししたいと思います。
先程、ご説明したように、諭旨解雇は、本来、懲戒解雇で退職金不支給のところを、会社が温情的な措置と講じての解雇とご説明しました。
しかし、解雇には変わりないので、会社がどんなに温情をかけたと考えても、労働者が解雇自体に納得していなければ、不当解雇の訴えを起こすことがあります。
その結果、退職金を支給していたとしても、解雇の妥当性、正当性が認められず、不当解雇と判断される場合もあります。
つまり、解雇が不当と判断される危険性は、どの解雇でも存在するのです。
退職勧奨とは?

退職勧奨とは、会社が労働者に自主的に退職届を出すように促すものです。
退職勧奨は、一般的には懲戒解雇、普通解雇、整理解雇を行う前段階に行われケースが多いと言えます。
ところで、退職勧奨とは、つまり「辞めてもらえませんか?」とお願いするわけですから、労働者は必ずしも退職勧奨に応じる必要はありません。
労働者が退職勧奨に応じなかった場合には、雇用契約は継続することとなります。
ですから、退職勧奨は、労働者の意思に関係なく雇用契約が終了する解雇とは、全くの別物となります。
また、労働者が退職勧奨に応じた場合には、雇用契約が合意で解除されたことになります。
この場合には、最終的に退職を申し出るのは労働者となるため、結果的には自主退社と同じ形となります。
そのため、後述します、解雇を行う時に必要となる労働基準法で定められた解雇予告期間や解雇予告手当の支払いは不要となります。
この点でも、解雇とは異なってきます。
ただし、退職勧奨の場合、雇用保険の手続きにおいて注意すべき点があります。
退職勧奨の雇用保険上の離職理由

先程、退職勧奨は、労働者からの自主退職の形となるため、労働基準法上、解雇には該当せず、そのため解雇予告期間や解雇予告手当の支払いは不要と書きました。
しかし、雇用保険上の離職理由は、形は労働者からの自主退職であっても、事業主の都合による解雇等(離職理由3)となります。
ここで注意が必要なのは、雇用保険制度の一環として行われている多くの助成金では、離職理由3で退職した労働者がいる場合、会社は一定期間助成金を受給することができなくなってしまいます。
また、助成金の対象労働者を離職理由3で退職させた場合には、既に支給している助成金を返還させるものあります。
助成金を利用する場合には、この点は注意が必要です。
さて、ここまで解雇の種類についてご説明してきました。
解雇は、通常、「懲戒解雇」「普通解雇」「整理解雇」の3つの種類に分けられます。
また、懲戒解雇に温情的な措置を講じる「諭旨解雇」、解雇の前段階として行われるケースが多い「退職勧奨」があります。
ところで、冒頭にもお話しましたが、解雇は、労働者にしてみれば、突然、生活の糧を絶たれてしまうため、死活問題となってしまいます。
そのため、労働基準法では、会社が労働者を解雇する場合には、解雇予告に関する義務を規定しています。
また、実際、労働者を解雇した結果、労働者が訴えを起こし、大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。
さらに、わが国では、労働者保護の風潮が強いため、解雇における裁判等は、会社側にとっては厳しい結果となるケースが非常に多いのが現状です。
ですから、解雇における手続きや注意点を正しく理解することは、経営上とても重要なことです。
ここからは、解雇における手続きや注意点等についてお話していきたいと思います。
解雇予告(解雇予告期間と解雇予告手当)について

労働者を解雇する場合には、労働基準法により30日以上の解雇予告期間を設けるか、即日解雇する場合には、平均賃金日額の30日分以上の支払い(解雇予告手当)をしなければならないと定められています。
なお、平均賃金の計算につきましては、ここでの説明を割愛させていただきますので、是非、こちらのブログをお読み下さい。
なお、解雇予告期間の日数の計算は、解雇予告の翌日から計算され、解雇の予告期間が30日に満たない場合は、満たない日分の賃金日額を支払えばよいとされています。
実際に具体的な数字を使ってご説明したいと思います。
ある労働者を4月30日に解雇したい場合には、3月31日までに予告をすれば解雇予告期間が30日となりますので、解雇予告手当の支払いは不要となります。
しかし、解雇を予告したのが4月15日の場合、4月16日から4月30日まで15日しかないので、この場合は、平均賃金日額15日分の解雇予告手当が必要なります。
また、4月30日に解雇の通知をした場合には、即日解雇となるため、平均賃金日額の30日分の解雇予告手当が必要となります。
この規定の趣旨は、解雇により労働者の生活の糧が立たれるわけですから、会社は少なくとも30日分の給与だけは面倒見てあげなさい、そうすれば、その間に労働者は次の就職先を見つけることができるから、というものです。
ところで、この手続きは法律規定となりますので、この規定に反して労働者を解雇した場合には法律違反なり、労働基準監督署の指導対象となりますのでご注意下さい。
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら
解雇予告(解雇予告期間と解雇予告手当)に対する誤解

実は、解雇予告に対して多くの経営者が誤解している点があります。
先程、労働基準法で労働者を解雇する場合には、解雇予告期間を設けるか解雇予告手当を支払わなければならない、と書きました。
これは、視点を変えれば、「解雇予告期間を設けるか解雇予告手当を支払えば、いつでも労働者を解雇できる。」とも読めます。
確かに先にも書きましたが、会社と労働者の関係は雇用契約であるので、契約を解除すること自体は基本的には違法行為にはなりません。
ですから、「解雇予告期間を設けるか解雇予告手当を支払えば、いつでも労働者を解雇できる。」という考え方自体は、間違っていないのかもしれません。
問題なのは、経営者が「解雇予告期間を設けるか解雇予告手当を支払って解雇すれば、何の問題も無い。」と誤解してしまう点です。
解雇予告は、あくまで労働者を解雇する場合の手続きであって、法律の規定通りに解雇予告期間を設ける又は解雇予告手当を支払って労働者を解雇しても、労働者から不当解雇の訴えを起こされる可能性があり、その結果、解雇理由の妥当性、正当性が認められなければ、解雇が無効の判断がされてしまいます。
つまり、労働者を解雇する場合には、解雇予告よりも解雇理由に妥当性、正当性が有るのかを十分に検討する必要があります。
ですから、安易に労働者を解雇してしまうと、本当に大きな労働トラブルに発展してしまう恐れがあるのです。
では、労働者を解雇する場合に、大きなトラブルを生じさせないためにはどうすればよいのでしょうか?
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら
解雇トラブルを防止するには・・・?

労働者を解雇した場合に、労働トラブルを完全に避けるには、労働者が不当解雇の訴えを起こし裁判等に発展しても、解雇の理由の妥当性、正当性が認められることです。
しかし、解雇理由の妥当性、正当性の基準は、法律で規定されているわけではないので、事案ごとに判断されるため、どうすれば解雇理由の妥当性、正当性が認められるかは、非常に難しいところがあります。
また、わが国では、労働者保護の風潮が非常に強いので、正直、解雇トラブルでは、経営者にとっては非常に厳しい結果となってしまうケースが多いと言えます。
ですから、労働者を解雇した場合に、100%トラブルを防ぐことは不可能に近いので、考え方としては、いかにして、裁判等で解雇理由の妥当性、正当性を認めてもらう可能性を高めるかが重要と言えます。
以下、裁判等で解雇理由の妥当性、正当性を認めてもらう可能性を高める上で重要なポイントをいくつかお話ししたいと思います。
就業規則等で解雇の根拠を定める
解雇理由の妥当性、正当性を争う場合に、解雇根拠の有無が重要なポイントとなってきます。
これはどういうことかと言いますと、就業規則等にどのような場合に普通解雇、懲戒解雇、整理解雇となるのかを規定しておくことが重要なのです。
もちろん、就業規則等に規定すれば、解雇理由の妥当性、正当性が必ず認められるわけではありませんが、規定が無ければ、経営者にとって非常に不利な状況となります。
ここで注意しなければならない点は、就業規則の作成義務が無い常時労働者数10人未満の会社においても同じ考えが取られます。
常時労働者数10人未満の会社は、就業規則が無くても労働基準法違反とはなりませんが、解雇裁判においては、就業規則がないために解雇の根拠が無いことについて便宜が図られることは基本的にはありません。
ですから、、就業規則の作成義務が無い常時労働者数10人未満の会社であっても、就業規則を作成する必要性は十分あります。
客観的証拠と改善の機会
解雇の裁判等において重要な位置付けとなるのが、客観的証拠と改善の機会です。
どんなに経営者が解雇の理由の妥当性、正当性を訴えても、それを裏付ける客観的な証拠が必要なければ、裁判等で経営者の訴えを認めてくれることは、まず無いと言えます。
それと同時に整理解雇以外の解雇では、どれだけ労働者に改善の機会を与えたかが重要な判断材料となります。
となると、必然的に労働者を解雇する以前に、解雇以外の懲戒処分を重ねることによって、その都度、改善の機会を与えることが重要と言えます。
また、その結果として客観的な証拠も積み重なってくると言えます。
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら
まとめ

今回は、解雇の種類と解雇の手続き等についてお話ししました。
繰返しになりますが、どのような解雇であっても、大きな労働トラブルへ発展してしまう可能性があります。
ですから、解雇に関して正しい知識を有することはとても大切なことなのです。
また、それと同時に早い時期から専門家に相談することも解雇トラブルを回避する重要なポイントと言えます。
是非、今後のご参考になさって下さい。
なお、当事務所では、解雇トラブルを回避するための無料レポートを発行しておりますので、お気軽にご利用ください。
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら

