会社を守る就業規則 7つのポイントとは・・・?

労働トラブルから会社を守るには、就業規則が不可欠だと言われます。
確かに、就業規則は、会社を守る唯一のものです。
では、会社を守る就業規則を作成するには、どのようなポイントに注意したら良いのでしょうか?
本ブログでは、「会社を守る」という視点から、就業規則の作成のポイントをまとめてみました。
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら
会社を守る就業規則 ポイント① 法律の基準を基本に作成する
就業規則は、会社を守る唯一のものです。
では、実際に「会社を守る就業規則」を作成するには何を注意すれば良いのでしょうか?
ここでは、就業規則を「会社を守る」という視点から、注意すべきポイントをいくつかお話ししていきたいと思います。
就業規則を作成する場合、労働時間や、休憩、有給休暇等、労働基準法等の法律の制限を受ける項目があります。
このような法律の制限を受ける項目を規定する場合、法律の基準を下回ることはもちろん許されません。
しかし、法律を上回る基準を定めることは、全く問題ありません。
例えば、有給休暇を法律の基準以上に付与するとか、定年を70歳までにするなどが考えられます。
しかし、ここで注意することがあります。
法律を上回る基準にすること自体は、良いのですが、もし、法律を上回る基準にする場合には、会社としてよく検討する必要があります。
と言うのは、就業規則は、たとえ、法律の基準を上回っていたとしても、一度、定めてしまうと、従業員の既得権益となってしまって、いくら法律の基準に戻すと言っても、従業員にとって不利益な変更となる場合には、会社は、一方的に変更することは出来ないのです。
少し矛盾するように思えるかもしれませんが、法律上はこのような取扱いがされます。

ですから、就業規則を作成する場合に、安易に法律の基準以上の内容で規定してしまうと、後々になって、会社にとって大きな負担となってしまう場合があります。
就業規則を作成する目的には、労働条件を明確にして、従業員に安心感を与えることもあります。
「できない約束」をしてしまうと、かえって、従業員に不安を与えることとなってしまいます。
従って、就業規則を作成する場合には、まず、法律の基準を基本に作成し、その後、会社の体力や実情に合わせて、変更していくことをお勧めします。
会社を守る就業規則 ポイント② 従業員の区分を明確にする
従業員には、正社員を初め、パートタイマー、アルバイト、契約社員といった、いくつかの区分があります。
そこで、就業規則を作成する場合、それぞれの条項が、どの区分の従業員に適用されるのかを明確にしておく必要があります。
ところで、労働基準法には、正社員やパートタイマー、アルバイトといった区分はされていません。
労働基準法では、全て「労働者」として取扱われます。
ですから、法定労働時間や時間外割増賃金、有給休暇などにつきましては、正社員同様パートタイマーやアルバイトにも同じ権利が発生します。
従って、就業規則においても、労働基準法の制限を受ける条項については、パートタイマーやアルバイトだからと言って、法律基準以下の扱いをすることは許されません。
しかし、法律の制限を受けない条項、例えば、賞与、退職金、休職制度、慶弔休暇などは、正社員とパートタイマー、アルバイト等と異なる扱いをしても法律上、問題はありません。
ただし、ここで注意しなければならないのは、正社員とパートタイマーやアルバイト等で異なった扱いをするのであれば、その旨をしっかりと明記する必要があります。
就業規則は、全ての従業員に適用されるのが、基本です。

ですから、本来は、従業員の区分によって、異なる取扱いをするつもりであっても、それが明記されていなければ、就業規則の内容が、全ての従業員に適用されることとなります。
例えば、「賞与や退職金は、パートタイマーやアルバイトには支給しない」とか「休職制度や慶弔休暇は、パートタイマーやアルバイトは利用できない」といった扱いをしたいのであれば、その旨を就業規則に明記しておく必要があります。
もし、その旨が明記されていなければ、パートタイマーやアルバイトにも賞与や退職金を支払わなければならなくなったり、パートタイマーやアルバイトも休職制度や慶弔休暇を従業員に与えられた権利として利用できることとなってしまいます。
就業規則を作成する際には、それぞれの条項が、どの区分の従業員に適用されるのかを十分に検討し、しっかりと明記しておくことが非常に重要となります。
難解な労務管理知識をわかりやすく解説!毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく完全無料メールセミナー「労務365日」のご登録はこちら
会社を守る就業規則 ポイント③ 服務規程について
会社には多くの従業員が働いています。人は、考え方がそれぞれ違うため、従業員が多くなれば、会社内の秩序を保つために、「一定のルール」が必要になってきます。
それが就業規則となるのですが、「従業員が守るべき一定のルール」という視点から見た場合に最も重要となってくるのが、「服務規程」と言えるでしょう。
服務規程を作成する際に、是非、覚えておいていただきたいポイントが1つあります。
それは、経営者の方が、従業員に守ってもらいたい事項を具体的により多く列挙することです。
服務規程は、労働基準法等の法律の制限を受けることはありませんので、公序良俗に反しない限りどのような事項を書いても、基本的には問題ありません。
ですから、服装や髪の色や男性で言えばひげ、女性で言えばマニュキアを禁止する規定を定めることもできます。
私が、経営者の方と服務規程の打合せをする際に、「こんな基本的なことは言わなくても、普通はわかるはずだ」といった声を聞きます。
確かに、小学校の校則ではないので、そう思いたくなる気持ちもわかります。

ただ、先程、書きましたように、それぞれ人は、いろいろな考え方をします。
ですから、従業員全員が、必ずしも経営者の方と同じ方向を向いてくれるとは限りません。
また、人は、物事も自分の都合の良い方向に考えるところがあります。
元々、服装やひげ、マニュキアを規制する法律はありません。
日本では、服装等に関しては自由が保障されています。
ですから、会社内で服装に関してのルールがなければ、たとえ、これまでは、各従業員の良識の範囲で一定の秩序が保たれていても、ある時、それを破る従業員が出てくることもあり得るのです。
しかし、そのような時に、極端な話し、「どうしてこの服装が悪いのですか?根拠を示して下さい。」と言われたら、返すことができなくなってしまいます。
「そんなバカバカしい」と思われるかもしれませんが、しかし、実際にトラブルが起こる時には、経営者の方、いや一般常識から考えても「バカバカしい」と思えることが原因となってしまうものです。
就業規則の服務規程については、条文の数が多くなっても良いので、より具体的により細部にわたって記載することが重要となってきます。
会社を守る就業規則 ポイント④ 慶弔休暇について
従業員が結婚する場合や、従業員の父母等が亡くなった場合に、一定の日数休暇を取ることができる制度を設ける会社も多くあります。
いわゆる慶弔休暇制度と呼ばれるものです。
この慶弔休暇につきましては、法律的には特別の定めがありませんので、慶弔休暇制度を設けるか、設けいないかは会社の自由となります。
つまり、慶弔休暇制度が無くても法律的には何の問題もないのです。
ですから、慶弔休暇制度を設ける場合でも、日数や対象となる家族や休暇中の給料につきましても、会社が自由に決めることができます。
ただし、ここで注意しなければならないのは、慶弔休暇を一旦就業規則に定めてしまうと、それが元々、会社の義務でないものであっても、従業員の既得権 となってしまいます。

例えば、「慶弔休暇期間中の給料を支払う」と定めたものを「支払わない」と会社が一方的に変えることは出来ず、変更するには、従業員を代表する者との合意等が必要となってきます。
一般的に市販されているモデル就業規則の場合、慶弔休暇に関しては、取得することができる日数が長めになっている場合が多いようです。
モデル就業規則を見て、「慶弔休暇は、これ位の日数を与えなければいけないんだ」と思ってしまう経営者の方も多いようです。
慶弔休暇を、会社の実情以上の内容で定めてしまうと、かえって会社や他の従業員の負担となってしまうことも考えられます。
従業員にとって慶弔休暇は、重要な労働条件となってきます。
就業規則を作成する場合、慶弔休暇につきましては、自社の実情にあった、無理の無い内容で定めることが重要となってきます。
会社を守る就業規則 ポイント⑤ 家族手当、住宅手当等について
労働トラブルの1つに残業代の不払いがあります。
実際に残業をしたにもかかわらず、残業代を支払わないのは、明らかな法律違反となりますので、これに関しては、トラブル防止とは全く別の次元の話しとなってしまいます。
しかし、残業代の不払いは、経営者の方の誤った解釈により発生する場合もあります。
その1つが、家族手当や住宅手当、通勤手当といった、いわゆる残業代を計算する場合に、支給総額から控除することができる手当に対しての誤った解釈です。
通常、残業代を計算する際には、基本給以外に支払われた各手当も含めた総支給額を基に計算されるのですが、労働基準法では、家族手当 住宅手当 子女教育手当 通勤手当については、残業代を計算する際に、支給総額から控除することができるとされています。
これらの手当が控除されれば、結果的に残業代を計算する際の単価が下がります
ただ、ここで注意しなければならないのは、名称が「家族手当」「住宅手当」「通勤手当」等であれば、どのような場合でも控除できるわけではありません。
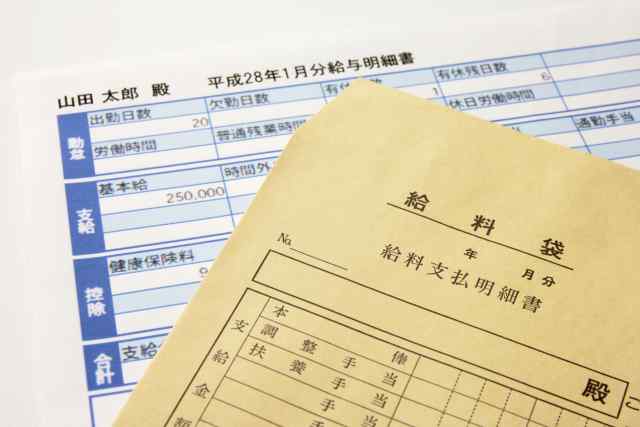
例えば、家族手当の場合でしたら、家族の数によって支給額を決めるとか、住宅手当の場合は、家賃や住宅ローン残高に応じて手当の額を定めるなど、支給する手当の額に根拠が必要となってきます。
つまり、例えば、家族手当の場合、名称は「家族手当」とされていても、家族数等を考慮されず、従業員に対して一律に支給されている場合や、「通勤手当」でしたら、通勤距離や手段等を考慮されずに一律に支給されている場合には、残業代を計算する際に、支給総額から控除できなくなってしまいます。
それにも関わらず、「家族手当で支給さえすれば、残業代を計算する際に、総支給額から控除できる」と誤った解釈をしてしまうと、結果的に残業代の不払いが生じてしまうこととなります。
ですから、就業規則を作成する場合に、もし、家族手当や住宅手当、通勤手当等の手当を支給する場合には、それぞれの手当の支給基準をしっかりと記載しておくことが非常に重要となってきます。
難解な労務管理知識をわかりやすく解説!毎日わずか3分で1年後、専門家レベルの幅広い知識が身につく完全無料メールセミナー「労務365日」のご登録はこちら
会社を守る就業規則 ポイント⑥ 就業規則の周知について
就業規則を「会社を守る」という視点で考えた場合、服務規程や解雇規程、休職制度等についてよく検討をすることはもちろん重要ですが、それとはまた別の次元で重要な要因があります。
それは、就業規則を従業員に周知することです。
労働基準法で、就業規則を作成した場合には、すみやかに従業員に全員に周知することが定められています。
つまり、就業規則というものは、従業員に周知して初めて、その効力を有することとなるのです。
逆に言えば、長い時間検討を重ねて作成した就業規則であっても、それを従業員に周知しなければ、極端な話し、「文字が印刷された単なる紙」に過ぎないのです。

例えば、従業員を会社内で守るべきルールである服務規程に反する行為をした場合に、何らかの罰則を与えようとした場合に、その内容が、たとえ就業規則にしっかり記載されていても、就業規則を周知していなければ、就業規則自体の効力が認められないため、罰則を与えることができなくなってしまう場合があります。
ですから、就業規則を作成した場合には、必ず従業員に周知することを行うようにして下さい。
この周知は、「会社を守る」という視点から考えた場合、非常に重要なポイントですので、是非、正しくご理解下さい。
なお、周知の方法ですが、これは必ずしも就業規則のコピーを従業員全員に配布する必要はなく(もちろん、全員に配布することが最も望ましいことです。)、食堂や休憩室等従業員の見やすい場所に置いておく等で周知義務を果たしたこととなります。
会社を守る就業規則 ポイント⑦ 懲戒解雇規定について
就業規則を「会社を守る」という視点で考えた場合、やはり最も重要なポイントなってくるのが、懲戒解雇規定です。
解雇トラブルは、労働トラブルの中でも最も困難なトラブルに発展する可能性が高いと言えます。
懲戒解雇規定において、最も重要なことは、懲戒解雇事由をより具体的に列挙することです。
これは、裁判となった場合に、解雇が正当なものであるかどうかの判断に、懲戒解雇事由の具体性が、非常に重要視されるからです。
もちろん、懲戒解雇事由が、具体的に書かれているからと言って、全ての解雇の正当性が認められるわけではありませんが、具体的に書かれている方が、より解雇の正当性が認められる可能性が高くなります。

例えば、従業員が、窃盗罪で逮捕された時に、「刑事事件で逮捕された時」と具体的に書かれていた方が、単に「会社に多大な損害を与え会社の名誉を傷つけた時」というような少し曖昧に書かれた場合より、解雇の正当性が認められる可能性が高くなるのです。
残念ながら、どんなに検討を重ねた就業規則でも、全てのトラブルを防ぐことはできません。
出来ることは、いかにしてトラブルが起こる可能性を低くし、万一、トラブルが起こってしまっても、なるべく速やかに円満に解決できる内容の就業規則にすることです。
それには、様々な可能性を考え、少しでも不安な事があったら就業規則に記載し、また些細な事でも会社内で守ってもらいたい事項については、服務規程等に記載しておくことが重要となってきます。
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら
まとめ

就業規則は、会社を守る唯一のものです。
規定の内容如何によって効果は違ってきます。
就業規則を作成する過程で、今回ご紹介したポイントに注意して就業規則を作成すれば、その効果は、一段と高まると言えます。
是非、今後のご参考にしていただければと思います。
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら
【関連記事】 >>就業規則の絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項

